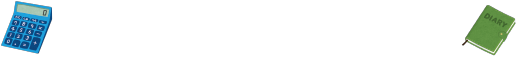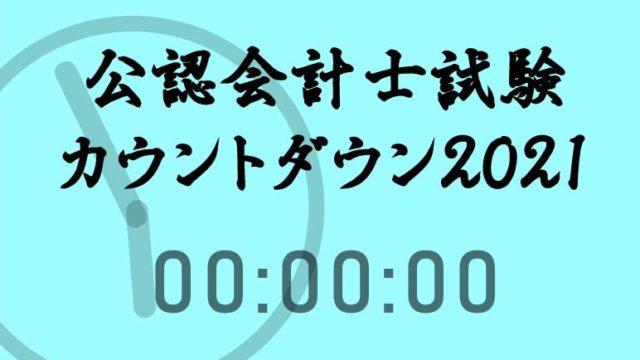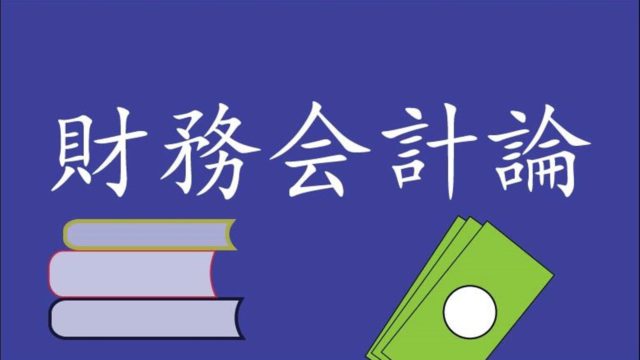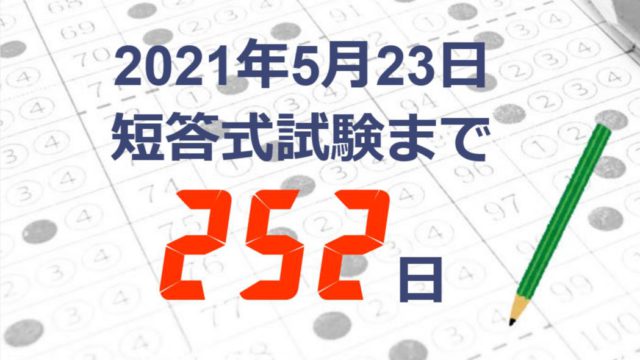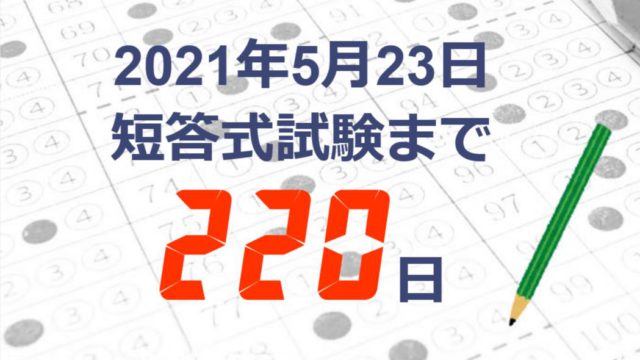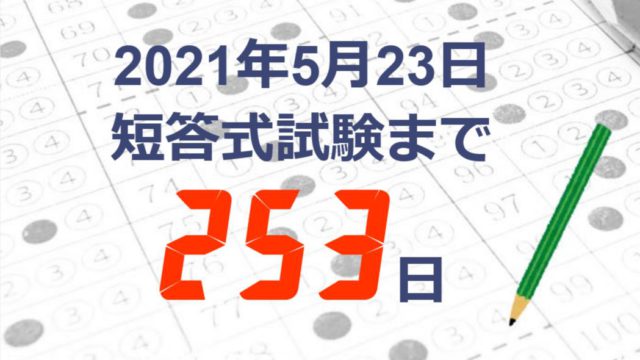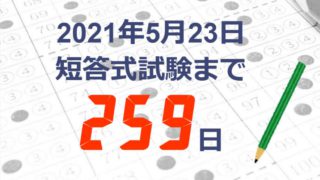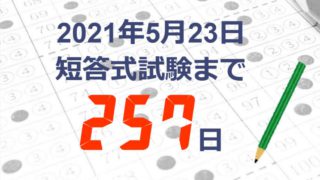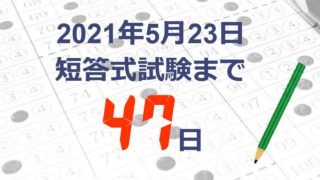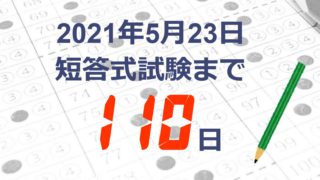目次
費目別計算
費目別計算は第一次の計算段階
材料費
- 材料副費
- 内部材料副費
- 外部材料副費
- 材料副費の予定配賦と材料副費配賦差異
- 購入原価
- 材料副費
- 割引・割戻(不明なものは材料副費の控除項目他、指示に従う)
- 非原価項目(棚卸減耗費)
- 予定受入価格と材料受入価格差異
- 予定受入価格の利点(4つ)
- 予定消費価格と材料消費価格差異
- 予定消費価格の利点(2つ)
労務費
- 給与支払総額
- 現金支給総額
- 給与計算期間と原価計算期間
- 直接作業時間、実働時間、就業時間、勤務時間、出勤時間
- 実際消費賃率
- 予定消費賃率と賃率差異
- 予定消費賃率の利点(2つ)
- 望ましい消費賃率とその理由
- 直接労務費の固定費化による二元的管理
経費
- 直接経費に含まれるもの(2つ)
- 複合費
- 経費の4分類
総合問題
- 材料費・労務費・経費のそれぞれの論点を組み合わせ、製造間接費勘定を完成させる問題
製造間接費
理論
- 配賦基準の種類(金額・物量)
製造間接費の予定配賦
- 予定配賦の種類と差異分析(固定予算・公式法変動予算・実査法変動予算)
- 基準操業度の種類(4つ)
論文対策
- 配賦基準の選択時の留意点(3つ)
- 製造間接費の予定配賦のメリット(2つ)
- 予定配賦の予算(固定予算・公式法変動予算・実査法変動予算)の比較(計算経済性・製品原価計算・原価管理)
部門別計算
部門別計算は第二次の計算段階
理論
- 部門別計算の目的(2つ)
- 原価部門を設定する際の留意点(3つ)
- 各原価部門の分類(4つ)
- 第二次集計の目的(2つ)
第一次集計
- 部門共通費の各部門への配賦
第二次集計
- 以下のパターンの組み合わせ(16パターン)
- 基準:単一か複数
- 月末の配賦方法:実際か予定
- 補助部門の配賦方法:
- 直接配賦法
- 階梯式配賦法
- 相互配賦法・簡便法
- 相互配賦法・連立方程式法
第三次集計
- 製造部門費の予定配賦方法と配賦差異(固定予算・公式法変動予算(線形)・実査法変動予算)
- 補助部門費の製品への直接配賦(一般費・製品に直接用役を提供している部門)
論文対策の論点
- 補助部門の配賦方法(直接・階梯式・相互)のそれぞれの長所・短所
- 単一・実際、複数・実際、単一・予定のそれぞれの問題点
- 部門共通費の個別費化の方法と理由
個別原価計算
製品別計算は第三次の計算段階
正常仕損費
- 新たに指図書を発行する(直接経費処理)
- ①補修可能
- ②補修不能・すべて作り直し
- ③補修不能・一部作り直し
- 新たに指図書を発行しない(直接経費処理)
- 軽微な仕損(直接経費処理)
- 間接経費処理(発生部門に配賦)
その他の論点
- 異常仕損費
- 作業屑
- 原則:発生部門の部門費から控除(発生部門の配賦不利差異が減少する、有利差異が増加する)
- 例外①:直接材料費から控除(個別原価計算表と仕掛品勘定の数値が一致しない)
- 例外②:製造原価から控除
- 例外③:原価計算外の収益
- ロット別個別原価計算(単純総合原価計算のように解けば良い)
- 加工費の配賦
単純総合原価計算
正常仕損・減損の基本形
- 以下の評価方法と負担関係の組み合わせが出題される
- 評価方法:平均法・先入先出法
- 負担関係:
- 度外視法・簡便法:①終点②終点以外
- 進捗度加味度外視法:①月末<仕損②月末≧仕損③平均的に発生
- 非度外視法:①月末<仕損②月末≧仕損③平均的に発生
- 注意:負担関係によって、仕損品の評価額をどこで控除するかが異なる
異常仕損・異常減損
- 正常性概念
- 原価発生原因主義
応用論点
- 非度外視法における定点発生において、正常減損費を通過数量比で按分
- 非度外視法における仕損等の複数発生(定点と定点・定点と平均的発生)
- 副産物の処理(総合原価から控除・原価計算外の収益)
- 材料の平均的投入
- 減損の区間平均的発生(非度外視法)
- 減損率が安定している場合
- 純粋先入先出法
論文対策の論点
- 度外視法と非度外視法の比較
- 仕損・減損の発生地点と検査地点