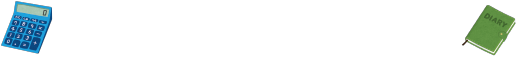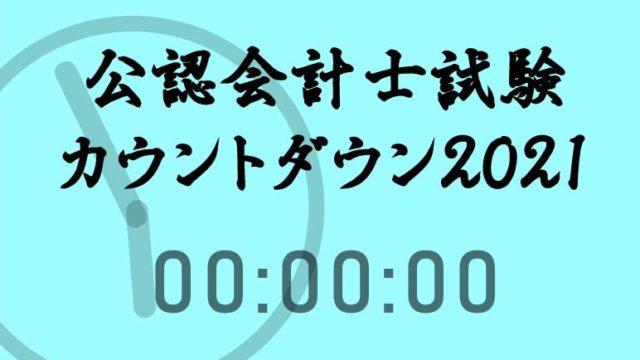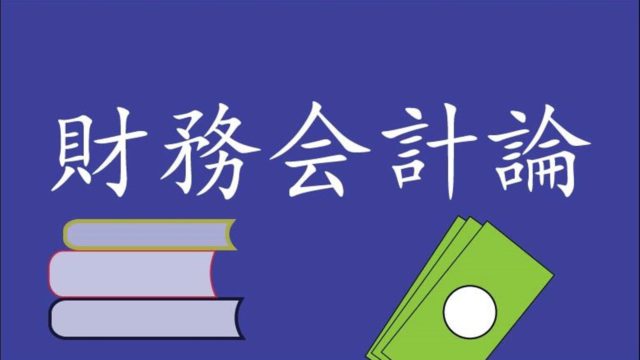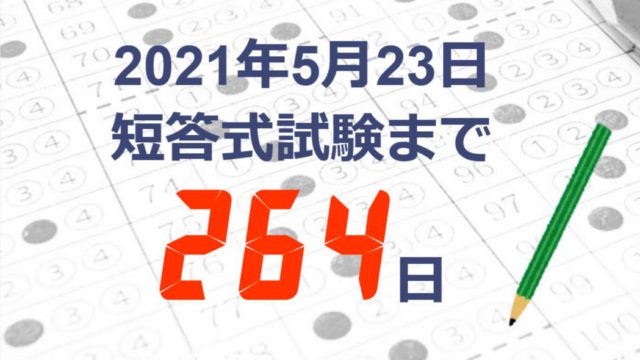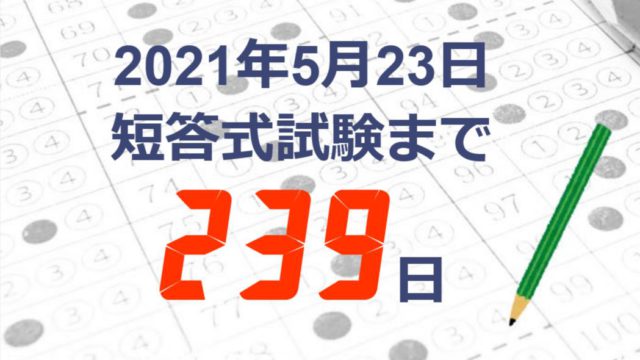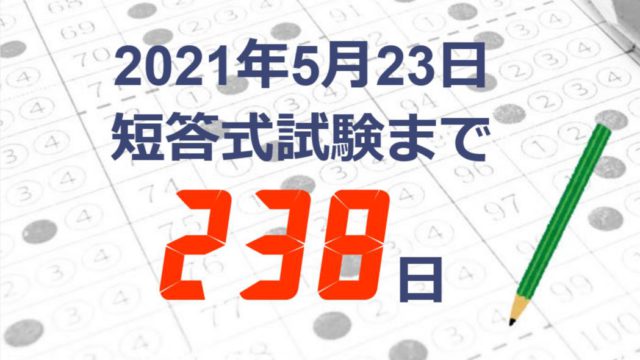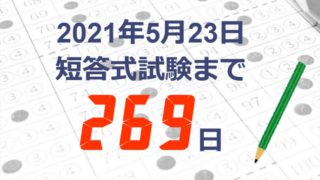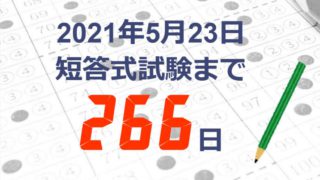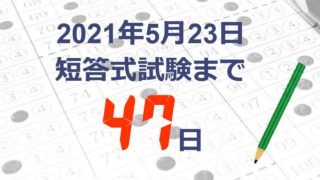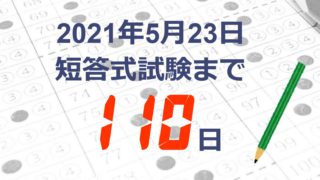短答式試験まで 267 日
論文式試験まで 356 日
目次
基準操業度
各基準操業度採用時の操業度差異の意味
- 実現可能操業度:操業度差異は非原価項目であるべき
- 正常操業度:操業度差異は繰延処理すべき
- 短期予定操業度:売上原価と棚卸資産に配賦する
- 注意:操業度差異は実務上売上原価・製品・仕掛品に配賦する。あくまで理論的にどうあるべきかを考えているだけ
部門別計算総論
部門別計算と単純個別原価計算
- 部門別計算とは:費目別間接費を原価部門別に分類集計する手続き。第二次の計算段階
- 部門別計算:製造間接費を部門別に分ける
- 単純個別原価計算:工場全体の製造間接費を総括配賦する
部門別計算の目的
- 正確な製品原価の計算
- 原価管理
部門設定時の留意点
- 正確な製品原価の計算ができる分け方 →作業の性質で一致させる
- 原価管理ができる分け方 →権限と責任で一致させる
- 計算経済性→部門の数を一定に抑える
- 注意:作業の性質での区分と権限・責任での区分が一致していない場合がある
部門の分類
- 製造部門
- 主経営部門
- 副経営部門
- 補助部門
- 補助経営部門
- 工場管理部門
- 補足:補助部門のうち補助経営部門は、相当の規模となった場合には計算上製造部門として取り扱う
第 1 次集計、第 2 次集計、第 3 次集計
- 部門別計算は第 1 次集計、第 2 次集計、第 3 次集計の 3 つのステップで行われる
- 第 1 次集計:費目別間接費を部門個別費と部門共通費に分け、部門共通費を部門個別費に配賦すること
- 第 2 次集計:補助部門費を製造部門費に配賦すること
- 第 3 次集計:製造部門費を各製品に配賦すること
第 1 次集計
第 1 次集計とは
- 費目別間接費を部門個別費と部門共通費に分け、部門共通費を部門個別費に配賦すること
第 1 次集計の会計処理
- 部門個別費(特定部門に直接跡付けられる原価)→ 当該部門に賦課
- 部門共通費(特定部門に直接跡付けられない原価)→ 関係部門に配賦
- 配賦基準:相関性・経済性・共通性を留意して選択
- 第 1 次集計後の各部門費=部門個別費+部門共通費の配賦額
部門共通費の配賦方法
- 原価要素別配賦法 →最頻出
- 原価要素群別配賦法
- 一括配賦法
第 2 次集計
第 2 次集計とは
- 補助部門費を製造部門費に配賦すること
第 2 次集計の目的
- 合理的な製品原価の計算
- 原価管理・責任会計に資するため
第 2 次集計の方法
- 直接配賦法
- 階梯式配賦法
- 相互配賦法
- 簡便法
- 連続配賦法
- 連立配賦法
| コスト | 厳密性 | 計算が簡単 | |
|---|---|---|---|
| 直接配賦法 | ◎ | ☓ | ◎ |
| 階梯式配賦法 | ☓ | △ | ○ |
| 相互配賦法(簡便法) | ☓ | ○ | ○ |
| 相互配賦法(連続配賦法) | ☓ | ◎ | ☓ |
| 相互配賦法(連立配賦法) | ☓ | ◎ | △ |
- 結論:
- 論点としてテストに出る:階梯式配賦法、相互配賦法(連立配賦法)
- 実務でよく使われる:直接配賦法
予想される問題
- 部門別計算の第1次集計
- 部門別計算の第2次集計(階梯式配賦法・連立配賦法)
今日やったこと
- 管理会計論の部門別計算の論点
- 管理会計論これまでのまとめ
- 財務会計論(計算)の売価還元法・退職給付会計・企業結合の復習
- 練習問題
明日やること
- 管理会計論の部門別計算の続きの論点
- 財務会計論(計算)の復習
- 財務会計論(理論)の復習