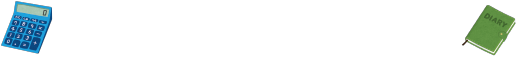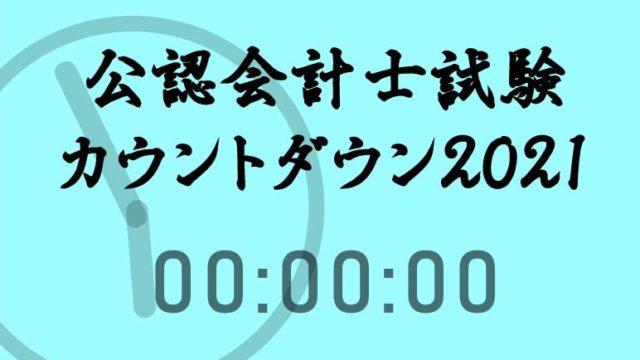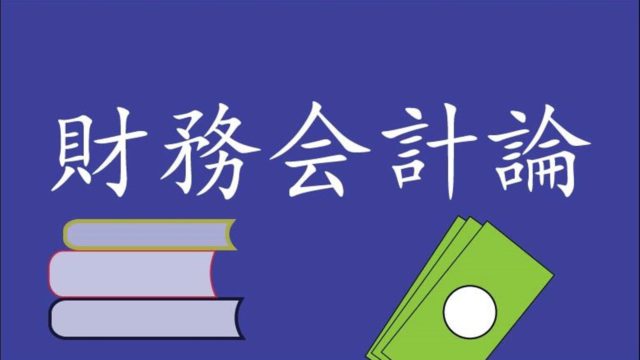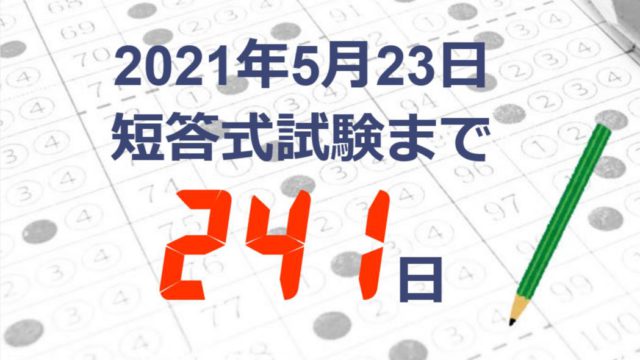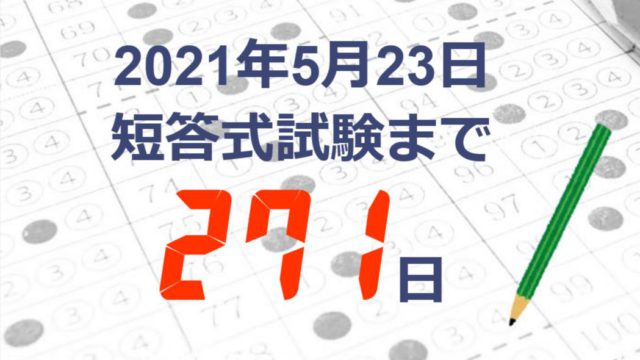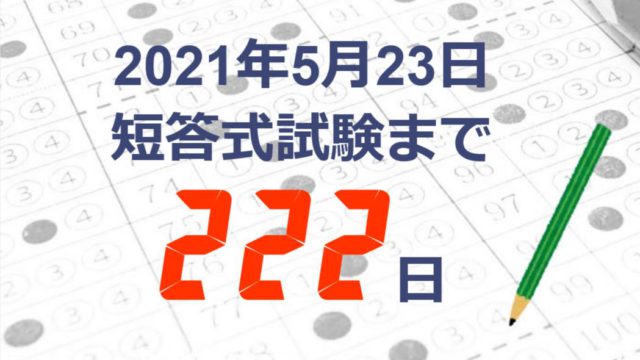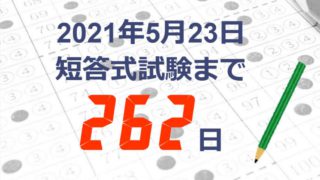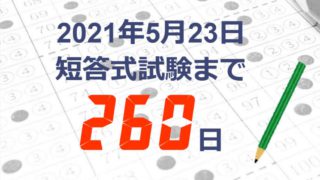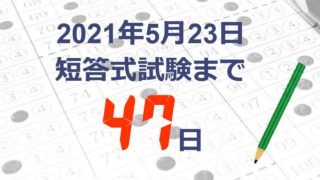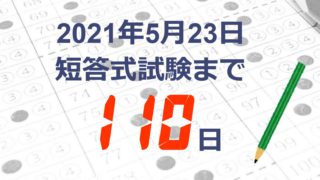短答式試験まで 262 日
論文式試験まで 351 日
目次
負債会計総論
負債とは
- 負債とは、過去の取引または事象の結果として、報告主体が支配している経済的資源を放棄もしくは引き渡す義務、またはその同等物をいう
- 近年定義された
負債の分類
- 法律上の責務
| 分類 | 例 |
|---|---|
| 確定債務 | 借入金、買掛金、支払手形、社債 |
| 条件付債務 | 退職給付引当金、製品保証引当金、返品調整引当金 |
- 会計的負債
| 分類 | 例 |
|---|---|
| 債務性のない引当金 | 修繕引当金 |
| 経過勘定項目 | 未払費用、前受収益 |
- 補足:修繕手引当金は、「経済的資源を引き渡す義務」に当たらないので、負債の定義からすると、負債に当てはまらない。
流動負債と固定負債
- 資産と同様
- 評価方法
- 1.正常営業循環基準
- 2.1年基準
引当金(負債)
引当金の定義
- 将来の特定の費用または損失に関するもの
- その費用又は損失の発生が、当期又はそれ以前の事象に起因している
- その費用又は損失の発生の可能性が高い
- その金額を合理的に見積もることができる
- 補足:繰延資産は「限定列挙」であったのに対し、引当金は上記の4条件を満たせば何にでも適用可
引当金の設定目的
- 適正な期間損益の算定
引当金の計上論拠
- 引当金は、費用の発生主義(実際発生主義)の観点からは認識すべきではない。ではなぜ計上する?
- 理由①:原因発生主義:発生主義を広く捉える
- 理由②:費用収益対応の法則:実際発生主義の立場をとっても認識すべきという立場
引当金の分類(P/L観点)
- 費用性引当金
- 論拠:原因発生主義、費用収益対応の法則
- 例:賞与引当金、修繕引当金
- 損失性引当金
- 論拠:保守主義の原則
- 例:債務保証損失引当金、損害補償損失引当金
- 収益控除性引当金
- 論拠:原因発生主義、費用収益対応の法則
- 例:売上割戻引当金(売上から控除)、返品調整引当金(売上総利益から控除)
引当金の分類(B/S観点)
- 評価性引当金
- 特徴:資産の部に計上され、特定の資産から控除される
- 例:貸倒引当金
- 負債性引当金
- 特徴:負債の部に計上され、債務性の有無で分類される
- 債務性あり:退職給付引当金
- 債務性なし:修繕引当金
引当金の測定
- 引当金の測定方法については明記していない
偶発債務と偶発損失(負債)
偶発損失
- 引当金の条件に合致する場合、引当金を計上する必要あり
偶発債務
- 注記が必要
- 例:債務保証
- 引当金の要件を満たす場合、引当金の設定が必要。注記の額は、引当金を控除した額を表示
偶発債務を伴わない偶発損失
- 偶発債務を伴わない偶発損失:貸倒
- 偶発債務を伴う偶発損失:債務保証
予想される問題
- 負債総論の論点(定義・分類)
- 引当金の論点(定義・目的・論拠・分類・測定)
- 偶発債務・偶発損失の論点
今日やったこと
- 財務会計論(理論)の答案練習
- 財務会計論(理論)の負債の論点
- 管理会計論の単純総合原価計算の仕損・減損の論点
- 管理会計論の単純総合原価計算の仕損・減損の練習問題
- 財務会計論(計算)の現金預金の復習
明日やること
- 財務計算の復習(企業結合・ストックオプション)
- 管理会計論の練習問題(部門補助費の配賦、単純総合原価計算の仕損減損)